船橋名産「ホンビノス貝」について詳しく調べてみた【後編〜漁に密着〜】
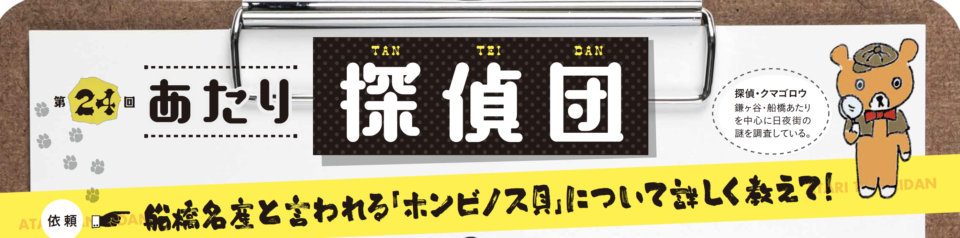
さて、前編では「ホンビノス貝」の基礎知識をご紹介しましたが、後編では実際に船に乗って、漁をしているところをレポートします。
漁協前からいざ出港!

この日は青潮が出ていましたが、ホンビノス漁は大丈夫とのこと。
東関道、京葉線の鉄橋を抜け船は漁場へひた走ります。


タンカー、間近で見ると迫力ありますね

左手にメリーチョコレート船橋工場が

サッポロビール千葉工場と南極観測船「しらせ」

地図だとこの辺
ここから少し右方向へ走ると、漁場に着きました。

漁師の柴田さん、おはようございま〜す

この辺まで来ました
漁の一連の流れ
①鋤簾(じょれん)という大きなカゴを投入します

鋤簾は重さ10kg、長さ4mと大きなカゴです

ドボンと沈めます
②船を巧みに動かしながら鋤簾(じょれん)を操り、砂の中にいる貝を採っていきます。

手に伝わる感触で、海中の様子を探る

③ある程度船を動かしたら、鋤簾(じょれん)を引き上げます。

ウィンチで海中から鋤簾を引き上げます

鋤簾の中の貝を船上にあげる

このツメで砂地を掻いていくのだそうです
④船上の貝を洗って選別し、網袋に詰めていきます。

貝を洗って選別する機械

網袋に入れていく
⑤港へ水揚げ、そして各地へ流通していきます。

船からベルトコンベアで陸へ

重さを計ります

トラックに乗せて出荷されていきます
船上で漁師の柴田さんにお話を伺いました。

漁師の柴田敬一さんは漁師歴20年。元々はアサリ漁をしていましたが、青潮の影響などで安定しないこともあったと言います。
最初は見向きもしなかったホンビノス貝ですが、今では市や漁協、飲食店のやPR効果もあって注目され、通年安定して漁ができるようになったのは嬉しいですねとのこと。
巧みに鋤簾を操っていたお手を拝見。

職人の手ですね
経験を積むと、海中の様子が手に取るようにわかると言います。鋤簾のツメにビニールゴミや、缶のプルトップが引っかかったのもわかるんだそうです。スゴイですね〜!
船橋の三番瀬が育む新たな名物「ホンビノス貝」。これからさらに全国的に広まっていくでしょう。
まだ食べたことがないという方も是非一度食べてみてください。


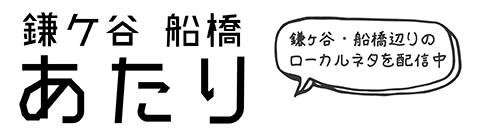




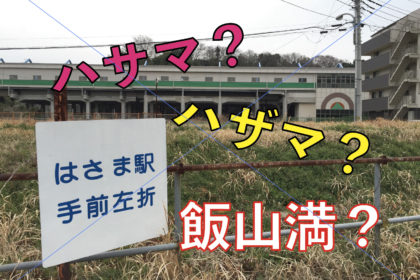
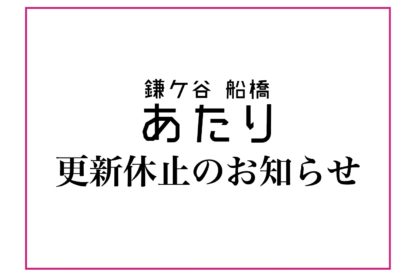



コメントを残す